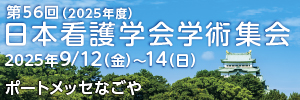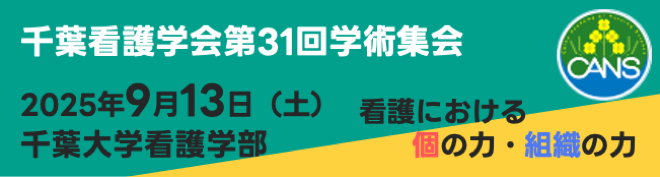Previous slide
Next slide
Menu

特別講演
人間のこころと身体・社会とのつながり「社会的痛み・共感・向社会行動 神経科学的アプローチ」
定藤 規弘(さだとう のりひろ)
立命館大学総合科学技術研究機構 教授
司会:岡田 志麻(立命館大学)
コミュニケーションは、人々の相互作用により多様な視点やつながりを生む可能性があり、「身体圏」という概念、即ち、身体を中心とした物理的、社会的、内的、情報的といった多層的環境との相互作用に含まれる。「身体圏」の概念は、進化と学習の軸を活用しながら、急速に変化する多層的環境への適応をwell-beingの追求として捉える枠組みを提供する(Sadato et al. 2025)。コミュニケーションの一つの定義として、「情報や考え、態度を共有することで相手の心の状態を変えること」がある。この共有の仕組みを理解するためには、模倣や社会的なつながり、共同注意、心の理論といった、向社会行動の発達に関わる神経回路を明らかにすることが重要である。現在、これらを対象にした機能的MRI研究が進んでいる。
向社会行動とは、他者を助けるための自発的な行動を指し、遺伝的に関係のない人々の間での役割分担や協力に重要な役割を果たす。この行動のメカニズムは、共感的な痛みの回避と社会的報酬の獲得という二つの側面で説明されてきた。共感的な痛みの回避は、他人の苦痛を共感し、それを避けようとする動機によって動かされると考えられている。一方、社会的報酬の獲得は、向社会行動が評判を通じて社会的な報酬を生み出し、良い社会的相互作用を促進することを示している。この過程で報酬系が活性化されることが、機能的MRIによって明らかになっている(Izuma et al. 2008)。これらは外部からの動機づけあるが、向社会行動の内発的な動機づけについてはまだ多くが不明である。
共感は、他者の感情を共有し、その理由を評価し、相手の視点を理解する能力として定義される。特に人間の向社会行動においては、相手の視点を取得することが重要であり、これによって共感的な喜びが増し、回避的な感情が抑制され、向社会行動が促進されることが脳機能イメージング解析によって明らかになっている(Kawamichi et al. 2016)。
共感的な喜びによる向社会行動の促進は、内発的な動機づけと考えられ、その起源は、発達初期に見られる母子関係における「相手を喜ばせること自体が報酬となる」社会的なつながりにあるとされている。この神経的な基盤を機能的MRIで調べたところ、初期視覚野から下前頭葉にかけての階層的な処理によって担われていること(Sasaki et al. 2018)、さらに社会的随伴性知覚が報酬であること(Sumiya et al. 2017; Miyata et al. 2021)が明らかになった。内発的な動機づけと社会的承認は、well-beingの本質的な要素であるため、これらの神経的な基盤を含めた理解の深化が求められている。
文献
Izuma K, Saito DN, Sadato N. 2008. Processing of social and monetary rewards in the human striatum. Neuron. 58:284–294.
Kawamichi H, Yoshihara K, Sugawara SKSK, Matsunaga M, Makita K, Hamano YHYH, Tanabe HCHC, Sadato N. 2016. Helping behavior induced by empathic concern attenuates anterior cingulate activation in response to others’ distress. Soc Neurosci. 11:109–122.
Miyata K, Koike T, Nakagawa E, Harada T, Sumiya M, Yamamoto T, Sadato N. 2021. Neural substrates for sharing intention in action during face-to-face imitation. Neuroimage. 233:117916.
Sadato N, Nakahara Y, Hirose M, Isaka T. 2025. The “Self” in a Multi-environmental Society: Creation of a New Academic Field of Body Sphere. 立命館大学スポーツ健康科学総合研究所紀要. 2:69–77.
Sumiya M, Koike T, Okazaki S, Kitada R, Sadato N. 2017. Brain networks of social action-outcome contingency: The role of the ventral striatum in integrating signals from the sensory cortex and medial prefrontal cortex. Neurosci Res. 123:43–54.
略歴
【学歴】
1983 京都大学医学部医学科卒業
1994 京都大学大学院医学研究科博士課程修了 医学博士
【職歴】
1983-1988 天理よろづ相談所病院ジュニアレジデント・放射線科シニアレジデント
1988-1990 米国メリーランド州立大学病院放射線診断科臨床フェロー
1993-1995 米国国立神経疾患卒中研究所 客員研究員
1995-1998 福井医科大学高エネルギー医学研究センター生態イメージング研究部門 講師
1998 同上助教授
1999-2004 岡崎国立共同研究機構生理学研究所大脳皮質研究系心理生理学研究部門教授
2004-2017 自然科学研究機構生理学研究所大脳皮質研究系心理生理学研究部門 教授(所属機関名称変更による)
2017-2023 自然科学研究機構 生理学研究所システム脳科学研究領域心理生理学研究部門 教授(組織名称変更による)
2023 立命館大学総合科学技術研究機構 教授
現在に至る